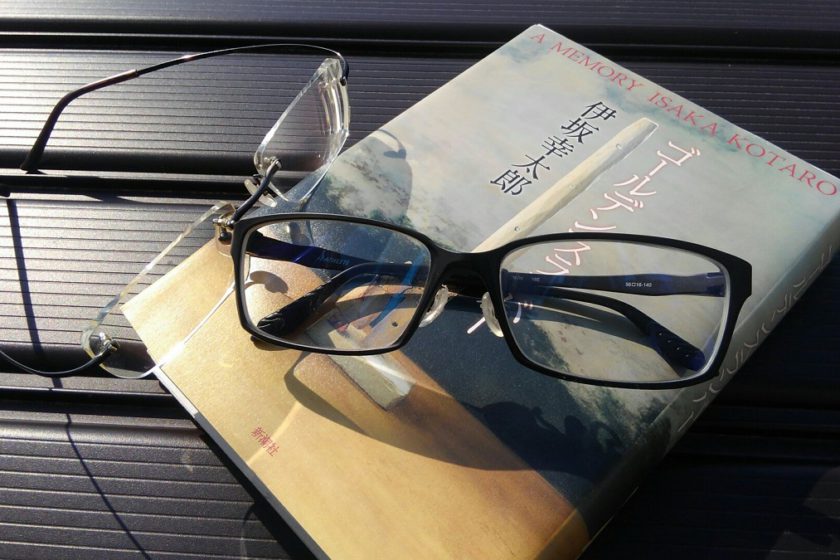沖縄のデパ地下はとても面白い
シーミーのウサンミの予約?
春の沖縄・唯一の街歩き
国際通りって、こんなに静かだったかなぁ。土曜日のお昼なのに、あんまり人がいない。那覇のメインストリートで沖縄最大の繁華街、そんな印象しかないから、肩透かしを食らった感じだ笑。
以前の記憶とは全く違って、建物も道もとてもきれいな街になっていた。もちろんゴミも落ちてない。当時は、観光客だけでなく地元の若者たちも遊ぶような元気な印象だった。大昔の闇市の面影とか、昭和感が満載で、昼間でも少し猥雑(わいざつ)な街だった気もする。
とはいえ、シーサーはもちろん、沖縄Tシャツを売る店、つまり沖縄っぽい土産物屋は、それなりにある。店頭で水着やビーサンを売っている店もあるのだが、人がいないから活気がないのだ。
まぁ昼は静かでも夜になれば賑わうのかもしれないな。そういえば、北に向かえばネオン輝く夜の繁華街「松山」がある。おっさんは、そっちはそっちで興味深い笑。

今日は、空き時間に少し街歩きでもしてみようか、そんな計画だった。那覇は混雑するから車ではなく、ゆいレール(モノレール)に乗って県庁前から国際通りへと向かった。でも街はそんな感じなので興味が薄れて、途中でUターンして戻ることにした。
どこかで珈琲ブレイクかなぁ、と店を探していたら、駅ビル?の地階にデパ地下みたいなスペースを見つけた。地元ならではの食材や総菜を売っていて、とても面白いのだ。ちなみにここはデパート「リウボウ」というらしい。
もちろんデパートだから、北野エースやアールエフワンなどの全国区のやつもあるのだが、食材コーナーには海ブドウはもちろん、ラフテー(豚角煮)やイナムドウチ(豚汁)、中身汁(豚ホルモン汁)などが大量に並んでいる。やっぱり沖縄だって、便利なパック商品は人気なのかな。

面白いのは沖縄の伝統食品や伝承料理を売る店があったことだ。店頭では沖縄天ぷらとか煮物、伝統菓子のチンピンやポーポー(ともに沖縄クレープ)などが売られているのだが、さらに面白いのは「お供え料理の予約販売」をしていたことだ。
お重のサンプル写真があるのだが、おせちのようなものではなく、少し地味な感じに見えた。まったく分からないのだが、沖縄の風習にちょっと興味が湧いたので調べてみることにした。
沖縄といっても地域ごとに色々違うみたいだが、これは(たぶんだが)「シーミーのウサンミの予約販売」ということだと思う。
うまく説明できないが、4月に行われる「シーミー(清明)」と呼ばれる大切な行事(三大お墓参りのひとつ)に使う、「ウサンミ(御三味)」という重箱料理らしい。お墓参りとしか書きようがないのだが、シーミーはお祝いに近い行事らしい。
親戚一同がご先祖様の墓前に集まって、ウサンミを囲んでワイワイご飯を食べるのだそうだ。現地の人はこれを「シーミーはお墓の前のピクニック」と説明するらしい、とっても驚いた笑。

何年か前だが、沖縄には「カジマヤー」という長寿祝い(97歳)の風習があることを知った。家の床の間に9升7合のお米を盛り、そこに9本の風車をたてるとか、派手に装飾したオープンカーで集落を走るとか、何やら地域ぐるみで主役を祝うファンキーな風習らしい。
ちなみにカジマヤーは風車のことで、童心に帰っていくという意味があるのだそうだ。高齢者を大事にするという沖縄の風習が今でもちゃんと根付いているんだと思う。
そういえば、この日の朝、沖縄のローカル新聞を開いたとき、いわゆるお悔やみ欄のページが、やけに派手に見えた。どの家も訃報のお知らせに大きく紙面を割いていた。書き方や内容も独特だった。
まぁ、その土地ごとに風習も作法も違うわけだが、沖縄ではこれが普通なのだろうと思う。生も死も、地域の人たちみんなで営むということかな。遠い昔から続く風習だろうから、どうか大事にしてほしいと思う。

結局、珈琲は飲めないまま帰路につくことになった。自販機を探したら、グァバやシークワーサーのジュースもあるのだが、そこに「琉球コーラ」というやつが並んでいた。炭酸がやや強めですっきりタイプのご当地コーラらしい。
そういえば以前の沖縄には、知らない名前のコーラがたくさん売られていた。アメリカ本土のローカルコーラばかりだった(概ねどれも美味しくない笑)。琉球コーラに興味があったが結局飲まなかった。こんな僕も歳をとったのかな。
いずれにしいても、この日は、庶民の日常にある沖縄文化を垣間見た日ってことだ。沖縄はやっぱり面白い。